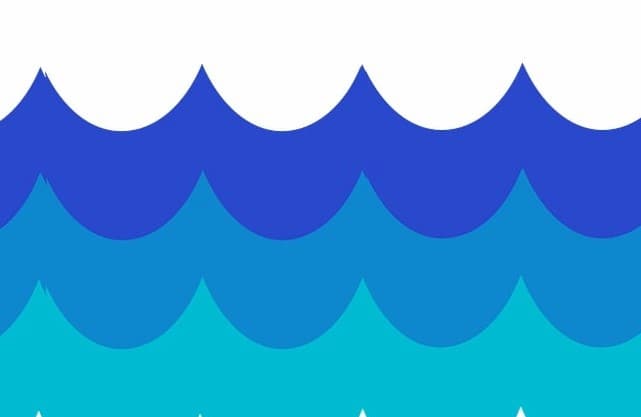なぜ太平洋と大西洋の境目には「紺色と緑色の海の境界線」のようなものができて、海水が混ざり合わないのでしょうか?
海流の向きや水温の違いもありますが、主には「密度」が原因です。
密度とは、単位体積あたりに存在する質量の値です。
太平洋と大西洋の水は、この密度の違いによって混ざり合うのに時間がかかるようですが、以下にその仕組みをできる限り分かりやすく紹介します。
太平洋と大西洋の境目
世界の海洋は名前で分けられていますが、実際には海は繋がっており、海水は混ざり合っています。
しかし、ある海の境界線のようなものを境に、それぞれ特徴の異なる光景が見られるのも事実です。
このような境界線は、川や氷河が海に注ぎ込む場所によく現れます。
例えば、太平洋と大西洋が出会う地点には、まるでお互いの海が混ざり合うことを嫌がっているかのように、濃く澄んだ藍色の海と濁った緑色の海の境目のようなものが見られることがあります。
これは、太平洋と大西洋の合流点、南米チリの最南端にあるホーン岬の沖でよく見られる光景です。
一体そこでは何が起こっているのでしょうか?
塩分濃度の差
海の塩分濃度(水に含まれる塩分の割合)は、世界の各地域の温度や降水量、水深や地形、淡水の流入量などによってばらつきがあります。
大西洋の海水表面は塩分を多く含むため、密度が高くなります。
一方、太平洋の海は塩分が少ないため、密度が低くなっています。
この塩分濃度による密度の差が、2つの海の間に「塩分躍層(えんぶんやくそう)」と呼ばれるバリアのようなものを作り出している可能性は否定できません。
時間が経てばいずれは混ざり合うかもしれませんが、海流の向きも異なることが、それを困難にしています。さらに、水温の違いや、氷河が溶けた水が淡水と海水の間に線を作ってしまうこともあります。
その結果、太平洋と大西洋は、簡単には混ざり合うのに時間がかかってしまう傾向があるのです。
海流のおかげで海の水は混ざり合う
地球の海にはそれぞれに特徴があります。
太平洋は、世界で最も深い海溝(マリアナ海溝)を含め、平均水深は4,280mと大西洋よりも深い世界最大の海洋です。
塩分濃度の低い深海からの水が流入しやすく、雨も多い太平洋は、大西洋よりも塩分が少なくなります。
一方で、大西洋の表層よりも、紅海や地中海のような閉鎖された海域の塩分濃度はさらに高くなります。深海の塩分濃度の低い海水が入りにくく、雨で補われるよりも早く水が蒸発してしまうためです。
基本的に、海水は深海でも表層でも混ざり合いますが、ときにどこからきた海水かによって質が異なるために、混ざりにくくなってしまうことがあるのです。
そして、興味深いことに、太平洋は、プレートテクトニクス(地球の表面を覆う岩盤の移動)によって毎年約0.52km2縮小しているのに対して、大西洋はその分拡大しています。
今回の記事は、海流をはじめ、地球規模でのダイナミックな地形の変動を実感できるちょっとした豆知識でした。