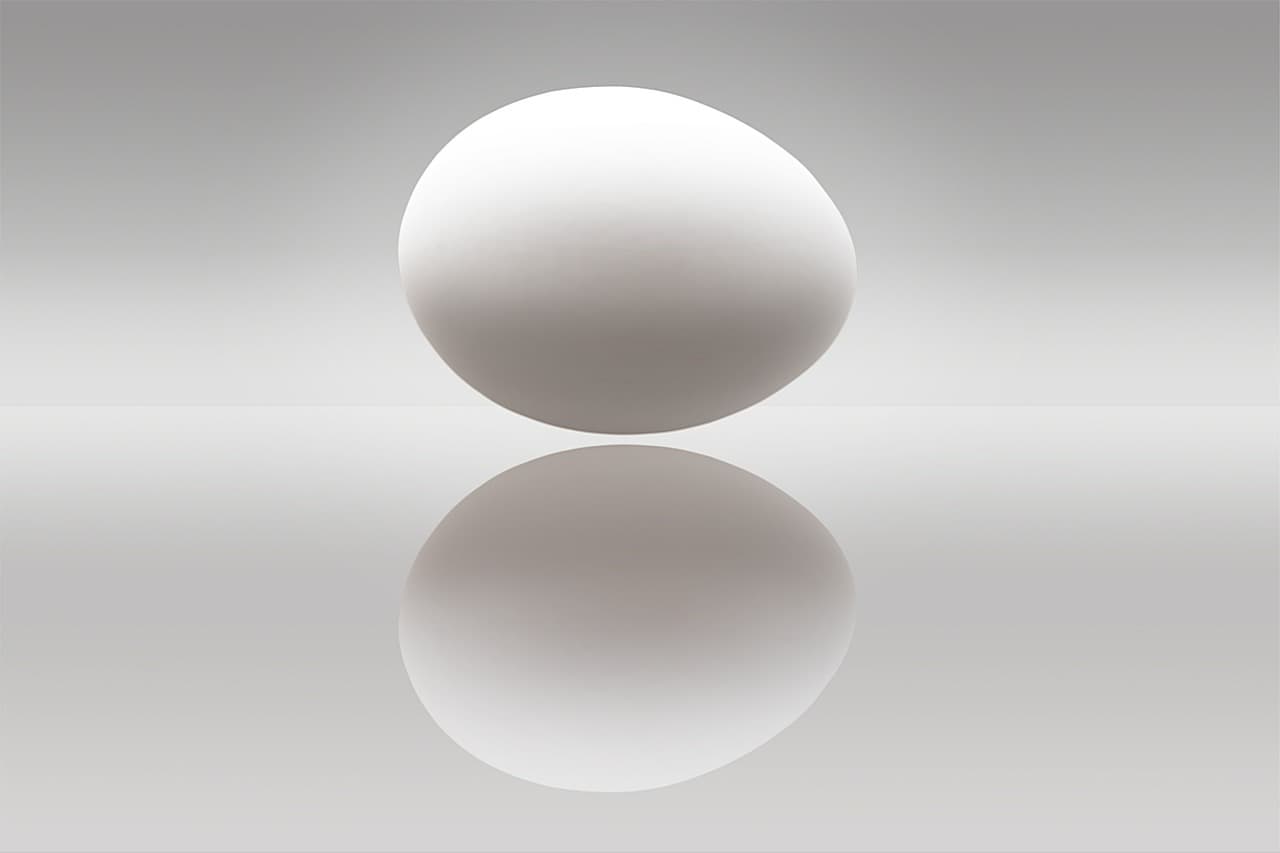今回は、卵の形がなぜ四角ではなく楕円に近い曲線を描くのか、また、鳥によっても卵の形が異なる理由など、卵形のおもしろい秘密について科学的に分かりやすく紹介します。

実は、鳥の卵の流線型は、強度を高めるだけでなく、空を飛ぶ鳥ならではの体の特徴が「卵形」に深い関係があることが研究分かってきたんだ。
卵形といえば、どのような形をイメージしますか?
おそらくほとんどの人が、丸くて、片方の端がずんぐりと太った「ニワトリの卵」を思い浮かべるでしょう。
たしかに地球上には、190億にも及ぶニワトリが、77億人の人間のために日々卵を産んでいることを考えると、毎日目にする卵が「卵形」というのは当然かもしれません。
しかし、実際には、卵を産む生き物は他にもたくさん存在し、みんな形が異なります。鳥の卵だけでも「卵形」と一括りにはできないほどさまざまな形があるのです。
鳥の卵は「卵形」と一括りにできないほど多様
2017年、科学者たちは1400種類の鳥から採取した5万個近くの卵の形をもとに、以下の分析をしました。
すると、ニワトリの卵は、他のどの鳥の卵と比べても、大きく異なる値を示し、ほとんどの鳥の卵が、ニワトリの卵のような形をしていませんでした。
なかには、フクロウのようなほぼ球形の卵もあり、ウミガラスのように海辺に住む鳥は円錐形だし、ハチドリの産む粒状の卵など、鳥の卵の形は、鳥の種類によって異なり、実に多様な形をしていることが分かったのです。
科学者たちは長い間、同じ鳥でも、種類によって形の異なる卵を産むのはなぜか、また、どのようにしてそうなったのかについて疑問でした。
では、そのナゾについて考える前に、まずは、卵の素晴らしさから理解しておきましょう。
殻付きの卵は、生き物の進化の技術革新
遡ることこと3億5千万年以上も前、陸地に生息するすべての骨格をもつ動物の祖先は、水の中から陸に這い上がり始めました。
そして、ある進化の技術革新が、陸上での生活に繁栄をもたらしたのです。
それは、殻付きの卵です。
両生類、爬虫類、魚類、虫、軟体動物、クモ、単細胞生物など、他の多くの動物が卵を産むなか、卵に殻が装備された種は、水辺から離れた環境でも繁殖を可能にしました。
殻付きの卵が、中身を乾燥から守る自給式生命維持装置として働いてくれたため、爬虫類や初期の哺乳類の祖先は 世界中に散らばって生育圏を広げることができたのです。
ハリモグラやカモノハシなどをのぞき、卵を産む哺乳類の祖先は最終的に、卵や赤ちゃんを育てる仕事をすべて体内に移していきますが、ワニ、カメ、ヘビ、恐竜などは卵のまま進化していきます。
卵の殻は革のようなやわらかいものから硬いものまでありますが、中でも特別な進化を遂げたのが鳥類の卵です。
四角い卵より曲線の方が強くて壊れにくい形
一見薄くてもろいイメージを受ける卵の殻ですが、実際には上からの押しつぶそうとする力に強く、人が乗っても壊れにくいといわれています。
この卵の強さの秘密は、殻の形にあります。
「カテナリー曲線」という言葉を耳にしたことはありますか?
ロープやネックレス、糸といった紐状の両端を持ったときにできる「たわみ」で、きれいな半円の形よりも張力と圧縮力を均等に分散させることができるため、イグルー(かまくら)を作るときにも取り入れられている曲線です。
この曲線を描いた強靭なシェル構造は、飛行機や自動車のボディ、ドームや橋の設計などにも採用されています。
殻に含まれる微細なタンパク質やミネラルのナノ構造とともに、この形状は、それが別の形状、たとえば四角や三角の卵であった場合に比べて強くなります。
卵形ってなに?
一般的に卵形は、文字通り「卵の形をしている」という意味の2次曲線、楕円形の意味で使われています。
しかし、実際の卵の形は、楕円の正確な幾何学的定義には当てはまりません。
少し専門的ですが、数学的に考えると、卵の形は、半径が異なる円同士の弧をつなげることによって作られ、対称性の軸を持っています。
この軸に沿って楕円を回転させると、卵形と呼ばれる形ができるのです。
実のところ、殻はこの形に強度を与えますが、実際に卵を形作っているのは殻ではありません。
卵の形は、殻ではなく内膜が作っていた
卵を酢など、炭酸カルシウムを豊富に含む液体に浸すと、酸の力によって殻は卵の形を保ったまま溶けます。
つまり、卵白と卵黄を覆うふにゃふにゃとした内幕(卵殻膜)だけでも、卵の形を維持するには十分なのです。
卵のでき方
卵は、受精していない卵細胞から始まり、それが卵黄に覆われて塊となった後、卵管と呼ばれる伸縮性のある管に押し込まれます。
それが卵管の中を移動するときに、精子によって受精し、卵黄の周りを卵白が包み込んで、まるで水風船のように液体で膨らむのです。
基本的に、卵の形は、膜(卵殻膜)が形成されたときに決定されます。
なぜ卵の形は、鳥の種類によって異なるのか
長年にわたり、科学者たちは、鳥の種類によって卵の形状が異なる理由について多くの仮説を立ててきました。
一つの仮説は、より球体に近い卵の方が、卵を覆う殻を作るのに必要な材料が少なくてすむためです。
他にも、母親が産む卵が複数ある場合、少ない面積で敷き詰めることができる形であれば、孵化まで効率的に卵の世話ができること。
また、崖の上に巣を作る鳥の場合は、片方がとがった卵は、巣の端から転がり落ちる代わりに、たとえ転がったとしてもその場で円を描くように転って元の位置に戻る傾向があるため、落下を防げることです。
これらは、科学者らが考え出した答えのほんの一部に過ぎません。
先が尖った卵の形は、鳥の飛行と関係があった
ある科学者が、異なる鳥類の種から採取した何千もの卵の形を分析したところ、形と飛行能力に最も良い相関関係を発見。
飛ぶのが上手な鳥は、体がより流線型に近いためそれだけ体のラインが細く、限られたスペースに臓器が密に詰まっています。
そのため、体内の管の中で、卵を作って搾り出すスペースにも限界があります。
実際にコンピューターでシュミレーションしてみたところ、膜の伸縮性と絞り出し方の2つを変えるだけで、事実上、あらゆる種の鳥の卵の形を作ることに成功しました。
そして、鳥類で最も一般的な卵の形は、完全な球よりもやや細長く、片側の先が少しだけニワトリの卵よりも尖った形でした。
先が尖った卵は、体が細い鳥にとっての自然な形の結果だったのです。
私たちは、先の尖った卵を産む最初の恐竜が鳥類を生み出したグループであることも知っています。
卵の形にはまだナゾが残されている
しかし、進化の仕組みについて覚えておくべき重要なことがあります。
私たちがすべての鳥を見たときに、「体の形が卵の形に影響を与える」という答えは最良かもしれませんが、それが唯一の答えであるという意味ではありません。
もしかしたら、他の異なる進化の利点を経て、尖った卵という形にたどり着いた鳥がいる可能性も否定できません。
親が細身でなくても、崖の端から転がり落ちにくい形であったり、親が卵を温めやすい形であったり、自然淘汰や進化は様々なレベルで起こり得るからです。
そもそも、すべての卵は卵形といえるのでしょうか?
卵形というからには、卵がどんな形をしていようが全て卵形だといいたい気持ちは分かりますが、実際に卵形はこれだという形はありません。
自然は様々な理由で様々な形を作ってきました。
結局、なぜ違う鳥が違う形の卵を産むのかという疑問は全て解決したわけではありませんが、科学というものは、そういうところからまだまだ発展していく可能性を秘めているのです。
もし全てに答えがあるとしたら、私たちは何の疑問も抱かず、新しいアイデアも生まれないでしょう。
世界には、まだ未解決のナゾがたくさんありますが、好奇心のままに考えてみるのも素晴らしいことかもしれません。