アヒルのような水鳥が、水をはじくために羽を(しっぽの付け根から出る)油でコーティングするのは有名ですが、実は、油がなくても、羽の構造自体が水をシャットアウトできることを知っていますか?
アヒルのような水鳥の羽は疎水性で、水をよくはじきます。
アヒルの背中に水を垂らすと、水が玉になって、するすると地面に落ちていきますね。
私たちはプールで泳ぐと、髪の毛は濡れてしまい、乾くまで時間がかかります。
しかし、アヒルは泳いでも羽は乾いたままで、ほとんど濡れることがありません。一体それはなぜでしょう?

たしか、水鳥は、水をはじくためにしっぽの付け根から出る油で羽をコーティングするんだよね。

それは有名な話ね。実はね、新たにおもしろいことが分かったの。
なんと油がなくても、羽の構造自体に水をはじく仕組みがあるらしいのよ。
今回は、水鳥の羽が水をはじく仕組みについて、サンフランシスコのカリフォルニア科学アカデミーで鳥類学と哺乳類学を研究するジャック・ダンバッハー氏の興味深い話を中心に紹介します。
どうやら水鳥の羽は、他の鳥の羽とは大きく異なるようです。
水鳥の羽にある隙間の秘密
鳥の羽は、基本的にダウン(下羽の綿羽)とコンター(輪郭のフェザー)という2つのいずれかに分類されます。
飛行するための羽と尾羽を含む輪郭の羽は、長くて硬い羽で、外敵に対する最初の防御線としても機能します。一方で、柔らかくふわふわしたダウンは、空気の層をつくることで保温性を高めています。
それでは、水鳥の羽を細かくみていきましょう。羽軸と数百本に枝分かれした羽根があり、間に隙間があります。
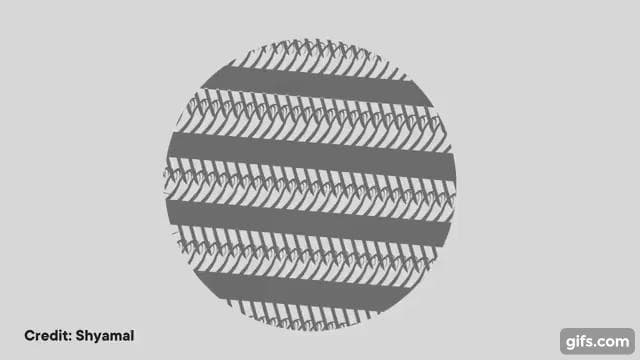
これらの隙間は、羽の中に空気を閉じ込める小さなポケットの役割をし、浮袋になるだけでなく、潜るときの抵抗を減らす助けとなります。
イタチなどの天敵に襲われにくい水の上で、体温が下がるのを防ぐ効果もあります。
さらに、上の図からも分かるように、それぞれの数百本の羽根は先にいくほど細くなり、くるんと丸まっています。これがマジックテープのように隣の羽とからみあって風や水に強いバリアを形成しています。
しかし、飛んだり、動いたりすると、このマジックテープがずれてしまい、羽根の裂け目から、空気や水が入り込んでしまうこともあります。これを防ぐために、鳥は定期的に羽毛の手入れ「羽繕い(はづくろい)」をする必要があるのです。
実は大変な作業「羽繕い(はづくろい)」
鳥は、尾の少し上にある尾腺から分泌される油をくちばしで羽につけて羽繕いします。
この油には、防水効果だけでなく、鳥の羽を傷つけるバクテリアから羽毛を守る細菌が含まれており、この共生細菌が羽毛に付着することで羽毛の早期摩耗を防いで潤いを与え、フックをよい状態に維持しています。
油をつけながら羽をブラッシングすることで、羽の柔軟性と強度を保ち、寄生虫からも守っているのです。
しかし、これは大変な作業で、種によっては、起きている時間の25%を羽繕いに費やすこともあるほど。
アヒルの羽毛は何層にも重なっている
そうはいっても羽繕いも完璧ではありません。
水鳥が深く潜るほどに、周囲からの水圧が高まってしまうため、自然とこの羽にある空気のポケットには水が押し込まれてしまうこともあるのです。

もし羽から水が浸み込んで皮膚まで達すると、アヒルはどうなってしまうの?

おそらく空気を閉じ込めたことによる断熱効果や水への抵抗を失ってしまうでしょうね。
でも、アヒルの羽毛には、それを防ぐためのさらなる仕掛けがあるのよ。
ハンガリーのデブレツェン大学の科学者たちによる2016年の研究から次のようなことが分かりました。
アヒルの体は、皮膚に水がつかないように、表面には水をはじく羽が覆い、その内側には軽くてやわらかい羽毛が何層にも重なってびっしりと生えています。
これについて、ハンガリー科学アカデミーのオルソラ・ヴィンチェさんは、「ガチョウなどの水生鳥は、陸生鳥に比べてより緻密で緊密な微細構造を持つ羽毛を多く持っている」といいます。
さらに、科学者たちは水鳥が水をはじく仕組みをより詳しく解明するために、圧力装置の中でアヒルの羽を重ねていき、その上に水を入れてゆっくりと圧力を上げながら、その様子をカメラで撮影しました。
圧力がかかると水は、最も簡単なルートを通って羽の隙間から押し入ろうとします。
しかし、羽の層が増えるほど、簡単に通り抜けられる隙間が並ぶ可能性は低くなり、水は皮膚まで達しにくくなります。
これは、生け垣の迷路を抜けようとするようなもので、羽の層を増やすと基本的に行き止まりが多くなり、水は立往生して閉じ込められてしまうのです。
空気を逃がさないための羽毛の構造を人工的につくる試み
そこで、研究者らは、さらに羽毛の構造の役割を再現してみることにしました。
レーザーで羽毛に似せてカットしたアルミホイルで人工羽毛を作り、細かな穴を再現し、それを何層も重ねて実験したのです。
結果的に、人工羽毛にも同様の効果が見られましたが、実に素晴らしいのは、水鳥が、常に空気のポケットを最適な状態を保つために、羽毛の層をちょうど良い数に調整している点です。
深く潜るアヒルは、深さによる大きな圧力に耐えられるように、より多くの羽毛の層を持っています。
高い撥水性を実現させるための3つの機能
研究者によると、このようなの羽毛の層は、おそらくほとんどの水鳥に存在するそうです。
なんという素晴らしいアイデアでしょう。アヒルは一日中水の中にいても濡れて体温が下がらないように、脱げないレインコートを着ているようなものなのです。
もちろん鳥の羽は完全な防水ではなく、鳥の種類によって水をはじく力も異なります。
まだ水をはじく羽をもたないヒナは、濡れて低体温症になりやすいため、親はヒナが濡れないようにしなければなりませんし、潜水性の鳥は、羽根の中に閉じ込められる気泡を少なくすることで、より効率的に潜水して速く泳ぐ工夫をしています。
このように鳥は、生育環境に合わせて、「羽毛の配列の整理」、「油を塗る」、「羽根ジッパーを閉めておく」この3つの適切な組み合わせにより、高い撥水性を実現させているのです。
アヒルの羽毛構造を船で実用化
研究者たちはまた、この実験で使った人工的なアヒルの羽を、私たちの生活で実用化させる可能性も示しました。
船の外側に、このアルミの人工羽のようなものをつけて、水の抵抗を減らしたり、フジツボの付着を防いだりすることへの活用です。
アヒルが水に濡れないというありふれた現象に、非常に優れた物理学が隠されていたなんて大きな驚きですね。


