 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物「大人のネコは人間にしか鳴かない」って知ってますか?
「猫は人間にしか鳴かない」って聞いたことはありますか?彼らは本当にネコ同士や他の動物に向かって鳴くことはないのでしょうか?今回は、ネコの鳴き声が人間のためだけにあるといわれる理由や鳴き声の原因について少しずつ分かってきたことを紹介します。
 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物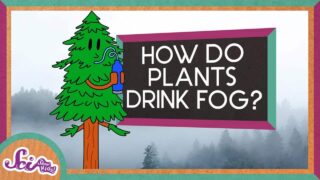 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物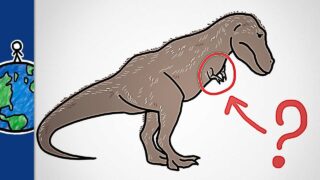 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物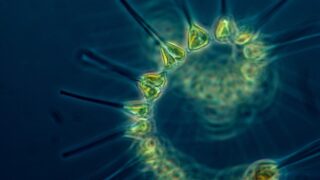 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物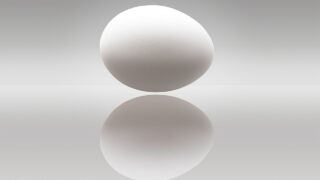 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物