 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物鳥はなぜ飛べるのか?翼のメカニズムとV字飛行
長い間研究者を魅了してきた鳥のV字飛行について、羽ばたきのタイミングや個々の配置場所によってエネルギー的な利益を最大化している仕組みをもとに分かりやすく紹介します。どうやら、鳥の飛び方の違いは、個々の鳥の大きさの違いが大きく関係しているようです。
 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物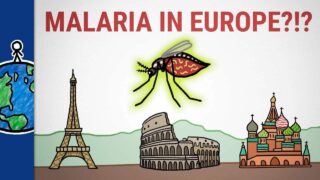 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物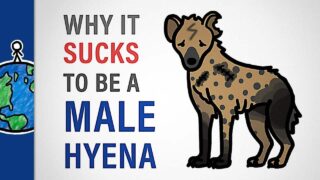 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物 動物・植物・生き物
動物・植物・生き物